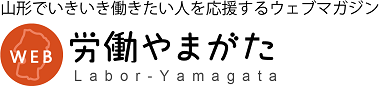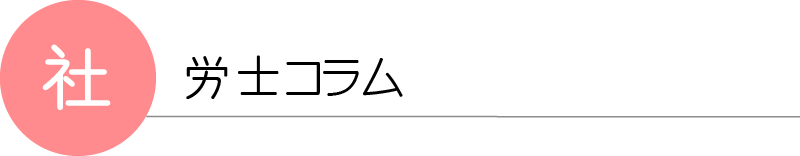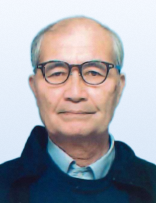現代は個人の価値観やライフスタイルが大きく変化し、それに伴い「働き方」もかつてないほど多様化しています。社会保険労務士の視点から、この「多様な働き方」の現状、メリット・デメリット、そして企業と従業員双方が留意すべき点など、これからの時代の働き方について述べてみたいと思います。
1. なぜ今、「多様な働き方」なのか?
「多様な働き方」が求められる背景には、次の3つの要因があると思われます。
① 労働力人口の減少と人材獲得競争の激化
少子高齢化が進む日本では、企業が持続的に成長していくためには、多様な人材を確保し、その能力を最大限に活かすことが不可欠です。従来の画一的な働き方だけでは、育児や介護を担う人々、あるいは特定のスキルを持ちながらもフルタイム勤務が難しいといった人材を取りこぼしてしまう可能性があります。
② 個人の価値観の変化
仕事に求めるものは、経済的な安定だけでなく、自己成長、社会貢献、ワーク・ライフ・バランスなど、より多岐にわたるようになりました。特に若い世代を中心に、柔軟な働き方を通じてプライベートの時間を充実させたい、複数のキャリアを築きたいといったニーズが高まっています。
③ テクノロジーの進化
ICT(情報通信技術)の発展は、時間や場所に捉われない働き方を可能にしました。クラウドサービス、コミュニケーションツール、セキュリティ技術の向上により、テレワークやリモートワークが現実的な選択肢となり、多くの企業で導入が進んでいます。
これらの背景から、企業は従業員のエンゲージメントを高め、生産性を向上させるためにも、多様な働き方への対応を迫られているのです。
2. 多様な働き方の具体的な制度例は?
多様な働き方の制度について、4つの柔軟性という観点から見てみましょう。
① 時間的柔軟性
• フレックスタイム制
一定期間における総労働時間を定めた上で、日々の始業・終業時刻を労働者が自主的に決定できる制度です。コアタイム(必ず勤務すべき時間帯)とフレキシブルタイム(自由に選択できる時間帯)を設けるのが一般的です。
• 時短勤務(短時間正社員制度)
フルタイムよりも短い所定労働時間で、正社員として働く制度です。育児や介護との両立支援策として活用されることが多くなっています。
• 週休3~4日制
1週間の休日を3~4日とする制度です。労働時間を維持したまま休日を増やすパターンや、1日の労働時間を長くして総労働時間は変えないパターンなど、様々な運用があります。
② 場所的柔軟性
• テレワーク(リモートワーク)
ICTを活用し、オフィス以外の場所(自宅、サテライトオフィス、カフェなど)で働く形態です。通勤時間の削減や、地方在住者の雇用機会創出にも繋がります。
• ワーケーション
「ワーク(仕事)」と「バケーション(休暇)」を組み合わせた造語で、リゾート地などで休暇を楽しみながら仕事も行う働き方です。
③ 雇用的柔軟性
• フリーランス・ギグワーカー
企業に雇用されるのではなく、個人事業主として特定のスキルや専門 知識を提供し、プロジェクト単位で仕事を受ける働き方です。
• 副業、兼業
本業とは別に、他の仕事を持つ働き方です。収入増加やスキルアップ、人脈形成などのメリットがあります。政府もモデル就業規則を改定し、原則容認の方向性を示しています。
④ 役割・キャリアの柔軟性
• ジョブ型雇用
職務内容を明確に定義し、その職務を遂行できるスキルや経験を持つ 人材を採用・配置する雇用システムです。成果主義との親和性が高いとされています。
• 社内公募制度・FA(フリーエージェント)制度
社内で新たなポジションやプロジェクトに挑戦する機会を従業員に提供する制度です。キャリア自律を促します。
これらの「働き方」は、単独で導入、あるいは組み合わせて運用されることもあります。
3. 多様な働き方のメリットは?
多様な働き方の導入は、従業員と企業双方に多くのメリットをもたらします。
○ 従業員側のメリット
• ワーク・ライフ・バランスの向上
柔軟な働き方により、仕事と育児・介護、趣味、自己啓発など、私生活との両立がしやすくなります。
• 通勤時間の削減、ストレス軽減
テレワークなどでは、通勤から解放され、空いた時間を有効活用できます。
• 自己成長の機会
副業や兼業などを通じて、新たなスキルや経験を得る機会が増えます。
• モチベーション向上
自身の裁量で働ける環境は、仕事への意欲や満足度を高めることに繋がります。
• 健康増進
睡眠時間の確保や、自分のペースで休憩を取れることなどが、心身の健康に良い影響を与える可能性があります。
○ 企業側のメリット
• 優秀な人材の確保と定着
多様なニーズに応える働き方を提供することで、採用競争において優位に立ち、離職率の低下も期待できます。
• 生産性の向上
従業員のモチベーション向上や、集中できる環境での業務遂行により、生産性が向上する可能性があります。
• イノベーションの促進
様々なバックグラウンドを持つ人材が、それぞれの能力を発揮しやすい環境は、新たなアイデアやイノベーションを生み出す土壌となります。
• オフィス関連コストの削減
テレワークの推進により、オフィスの縮小や賃料、光熱費などのコスト削減が可能です。
• BCP(事業継続計画)対策
自然災害や感染症拡大時にも、分散して業務を継続できる体制を構築できます。
• 企業イメージの向上
従業員を大切にする企業としてのイメージが向上し、社会的な評価にも繋がります。
4. 多様な働き方の課題と社会保険労務士の視点からの留意点とは?
事業者が導入・運用するにあたり、いくつかの課題や注意点が存在します。
• 勤怠管理・労働時間管理の複雑化
フレックスタイム制やテレワークでは、従業員の労働時間を正確に把握することが難しくなる場合があります。労働基準法を遵守した勤怠管理システムの導入や、始業・終業時刻の報告ルールの明確化が不可欠です。
特にテレワークでは、「中抜け時間」の取り扱いや、時間外労働の見えにくさといった課題があります。客観的な記録に基づく労働時間管理が求められます。
• 人事評価制度の見直し
オフィスでの勤務態度が見えにくいテレワーク環境下では、従来のプロセス重視の評価から、成果や貢献度を重視した評価制度への転換が必要となる場合があります。評価の公平性・透明性を確保するための基準設定や、評価者研修も重要です。
• コミュニケーション不足と孤立感
対面でのコミュニケーションが減少することで、情報共有の遅れや、従業員が孤立感を感じる可能性があります。定期的なオンラインミーティングの実施、チャットツールの活用、メンター制度の導入など、意識的なコミュニケーション機会の創出が求められます。
• 情報セキュリティ対策
社外で業務を行う機会が増えるため、機密情報や個人情報の漏洩リスクが高まります。セキュリティポリシーの策定と周知徹底、デバイス管理、セキュリティ教育の実施が不可欠です。
• 健康管理、メンタルヘルスケア
テレワークでは、長時間労働に陥りやすい、運動不足になりやすい、オンオフの切り替えが難しいといった健康課題が指摘されています。産業医や保健師との連携、オンラインでの健康相談窓口の設置、ストレスチェックの実施とフォローアップなどが重要になります。
• 就業規則、労使協定の整備
多様な働き方を導入する際には、それぞれの制度内容や運用ルールを就業規則に明記し、必要に応じて労使協定を締結する必要があります。例えば、テレワーク規程の作成、フレックスタイム制に関する労使協定の締結・届出などが挙げられます。これらは法的なトラブルを未然に防ぐ上で非常に重要です。
• 適用対象者の範囲と公平性
職種や業務内容によっては、多様な働き方の適用が難しい場合もあります。適用対象者と非適用者の間で不公平感が生じないよう、制度設計やコミュニケーションに配慮が必要です。
• 法的義務の遵守
労働基準法、労働安全衛生法、労働契約法など、関連する法律を遵守することが大前提です。例えば、テレワークであっても、労働時間に応じた休憩時間の付与、時間外労働に対する割増賃金の支払い、安全配慮義務などは免れません。
社会保険労務士は、これらの課題に対して、法的な観点と実務的な観点の両方から企業をサポートし、それぞれの企業の実情に合った制度設計や運用方法を提案していく役割を担います。
5. 多様な働き方を成功させるためには?
多様な働き方を成功させるためには、単に制度を導入するだけでなく、組織風土の変革や、従業員の意識改革も伴う必要があります。
• 経営層のコミットメント
経営層が多様な働き方の重要性を理解し、積極的に推進していく姿勢を示すことが不可欠です。
• 従業員への丁寧な説明と意見聴取
新しい制度を導入する際には、その目的や内容を従業員に丁寧に説明し、意見を聞く機会を設けることで、納得感と主体的な活用を促します。
• トライアル期間の設置
本格導入の前に、一部の部署や期間を限定して試行し、課題を洗い出して改善していくことが有効です。
• 管理職の意識改革とスキルアップ
部下の働き方が多様化する中で、管理職には、個々の状況に応じたマネジメント能力や、コミュニケーション能力、部下のキャリア自律を支援する姿勢が求められます。
• テクノロジーの活用
コミュニケーションツール、プロジェクト管理ツール、勤怠管理システムなど、多様な働き方を支えるテクノロジーを効果的に活用することが重要です。
6. おわりに
「多様な働き方」は、もはや一部の先進的な企業だけのものではありません。それは、個人の幸福を追求し、企業の持続的な成長を実現するための、現代社会における必然的な流れと言えるでしょう。
しかし、その導入と定着には、法的な整備はもちろんのこと、働く人と企業双方の理解と協力、そして不断の努力が求められます。社会保険労務士として、私たちは、企業が直面する様々な労務課題の解決を支援し、従業員一人ひとりがその能力を最大限に発揮できるような、そして個と組織が共に輝けるような職場環境づくりに貢献していきたいと考えています。
このコラムが、皆様の企業における働き方改革の一助となれば幸いです。
令和7年6月寄稿