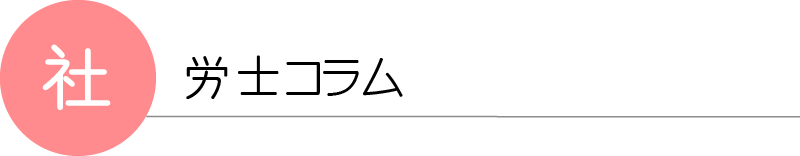ある日社労士事務所の電話が鳴った。何か困ったことがあると連絡をくれる、そんな社長さんからの電話でした。
「うちの男性社員が育児休業を取りたいと言っている。法改正がされたのは知っていたが、規定も直していないし、拒否したいがどうしたらいいか…。」
聞けば、若手の男性社員から、令和4年11月頃から産後の育児休業を申請したいと思っていると提案されたとのこと。出産予定日までは日もなく、会社の規定を見直す時間もないとのことでした。
令和4年10月1日から、育児休業とは別に、子の出生後4週間を限度に取得できる通称「産後パパ育休(出生時育児休業)」制度が始まり、多くの事業所が育児介護に関する規定の見直しを迫られている最中の相談でした。
社長には、法改正の趣旨を伝え、会社の規定よりも法律が優先するため、申請は拒否できないことや現在の社会情勢、そして雇用の確保・維持の観点からも、男性の育児休業取得を前提に会社の規定を見直すべきであることなどを伝えました。当初、頑なに男性の育児休業に否定的だった社長も、徐々に意識が変わり、若手の男性社員には産後パパ育休を取らせ、その後早い段階で会社の規定を改定することとなりました。
なぜ今、男性の育児休業促進なのか。多くの事業主からも問われた質問です。仕事と家庭を両立しようという意識の変化への対応や、女性の就労促進、家事育児負担の男女格差解消などの諸問題の一つの方策なのだろうと思われます。
現在の状況としては、少子化は進み、山形県を含む地方の労働力人口は恐ろしい勢いで減少しています。今まで目を向けられてこなかった「男性労働者の仕事と家庭の両立」という問題に一石を投じ、就労環境改善の小さな一歩になって欲しいと感じています。
男性育児休業に消極的な会社や経営者がいる一方、2022年の男性育児休業取得率は、前年度から大きく上昇し、47.5%になりました。(※一般社団法人日本経済団体連合会「男性の家事・育児」に関するアンケート調査結果より)
一方で、同アンケートでは家事・育児の促進への課題として「代替要員の不足」「アンコンシャス・バイアス(性別役割分担意識等の無意識の思い込み)の存在による家事・育児を両立しづらい職場風土」「長時間労働や硬直的な働き方」が挙げられており、一層の企業改革や、経営者や管理職の意識の変化が求められていると感じます。
働きやすい職場という言葉はあっても、内容は千差万別です。それは、働く人それぞれ一人ひとりが、抱える問題やサポートが必要な範囲が異なるからです。
また休みやすい業務内容や、代わってもらいやすい地位や部署など、働く環境もまた千差万別です。
今回の「産後パパ育休」に関しては、これまで拡充された育児休業とは独立して追加された休暇制度であり、まずは制度の側から休みやすい職場への転換を模索しているといえるでしょう。
すでに男性が育児に「参加」するという認識は、若い世代で薄れつつあり、男女が性差による役割分担にとらわれることなく、同じ目線で子育てをしたいという意識が芽生えつつあります。
「女性が休んで当然」「育児は女性の仕事」という経営者と管理職がいては、それだけで貴重な労働の担い手を失うリスクがあるのです。これまで相談を受けた中でも、経営者の無理解が原因で、離職・退職に繋がった事例もあります。
国も男性の育児休業取得率の増加のためには、経営者のメッセージが必要と考えており、育児に関連したトップメッセージを発することで、会社全体の雰囲気も大きく変わると期待しています。
今回の法改正では、産後パパ育休だけではなく、これまでの育児休業を分割取得できる制度や、産後パパ育休期間中の就労に関するものも含まれており、これまでの産休・育休制度からするとかなり複雑になった印象があります。
また、多様な働き方を進める一方で、社会保険に加入していなければ出産手当金の請求が出来なかったり、雇用保険に加入していない、もしくは加入期間が短いと育児休業給付金の申請が出来なかったりと、社会保障として手薄に感じる部分もあります。
育児休業給付金請求の簡素化や、現在検討されている育児休業給付金の増額など、労使双方にメリットとなる制度へ進んでいってほしいと思います。
※参考
一般社団法人日本経済団体連合会(経団連)「男性の家事・育児」に関するアンケート調査結果
https://www.keidanren.or.jp/policy/2023/040.pdf
令和5年11月寄稿